
- 赤ちゃんの検診で保健師さんに気になることを言われた。
- 義母が子育てについていろいろアドバイスしてきてストレスがたまる。
- ママとしてはおっぱいをまだやりたいけど、周りがそろそろやめろとうるさい。
- どうしたらいい?
そんなお悩みに答えます。
ママを傷つける!専門家からの心ないエビデンスもない「アドバイス」
自治体の検診や病院を受診したときなどに、看護師さんやお医者さん、助産師さん、保健師さんなどからこんなことを言われたことはありませんか?
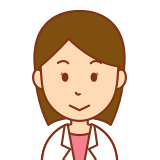
- 体重があまり増えていないのは母乳が出ていないせい。ミルクを足して
- 1歳過ぎたら母乳は水と同じ。栄養がない
- 虫歯になるから歯が生えてきたら母乳はやめるべき
- 長期授乳は流行りモノ
- おっぱいやめないから離乳食が進まないのよ。
- 早く離乳食を進めなきゃダメ
わたしも実際に言われたことあります。
これら、全て残念な指導です。
- おっぱいが出ていないかどうかを体重の増減だけで判断することはできません。
- 1歳過ぎても母乳は栄養満点です。
- WHOも離乳食は「補完食」といって成長とともに足りなくなった栄養を補うためのものと言っています。
- 離乳食の進みには個人差があります。早く進めたらいいというものではありません。
- おっぱいはなお栄養たっぷりで水にはなり得ません。
- また、長期授乳にはメリットもあり流行り物ではありません。
- 虫歯予防にはおっぱい以外の食べ物や歯磨きでリスクを下げられる
育児や医学の情報は日々研究が進み、解明されることも多いです。
でも、専門家によっては、知識をアップデートできずに何十年も指導をしてきている方たちもいるんですよね。
プロとして残念ですよね。
特に、医学に関わる方たちは日々研鑽を重ねて勉強しているイメージがあるので、特に残念に感じてしまいます。
しかも、実際に検診や病院でこんなこと専門家に言われたら気になっちゃいますよね。
ママは赤ちゃんを大事に思うあまり心配し過ぎてしまうこともありますもんね。
出産後は特にホルモンバランスが崩れて敏感になってしまうこともあります。
こちらも参考にしてみてください。
【古い知識】まだまだある!実母・義母・ママ友・親戚からの子育て「アドバイス」【エビデンスなし】
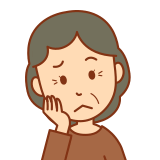
- 泣いてばかりなのは母乳が出ていないんじゃない?ミルクにしたら?
- お風呂上がりには白湯を飲ませないと・・・
- まだオムツ取れないの?
- 抱っこばかりしていたら抱き癖がつく
- 首座りが遅いんじゃない?など発達関係
- ハイハイしないのは抱っこばかりしているから
- 言葉が遅いんじゃない?
- 歩くのが遅いんじゃない?(どーせーっちゅうねん)
- 文字を書くのが遅いのはママの教育が悪い
こちらは、全くエビデンスはないですが子育て経験者が(おせっかいで)投げかけてくるアドバイス(もどき)。
皆さんもどれか一つは言われたことがあるのでは?
わたしは全て言われていますww
「まだオムツ取れないの?」
「言葉が遅い、ハイハイが遅い」
「まだひらがな書けないの?」
ってアレなんなの?
ママが悪いの?子どもには成長のペースがあんねん。
小学生になってもオムツしている人はいないしいいやん。ほっといて。と思います。
抱き癖がつくとか、心配しているようなていで来るのが一番タチが悪いですよね。
首座りが遅いなどの発達関係を責めてきてママの不安を煽ってくるあたり、悪意を感じます。
何世代も同居して、家族みんなで育児をしていた頃の古い育児習慣や、聞きかじった知識を押し付けてきたり、古くなった育児知識をひけらかしてきたりすることもあるので注意が必要です。
家族や親戚関係は長く続くものなので、遺恨を残さないように華麗なスルー術を身につけましょう。
【もっとゆるくていいんじゃない?】ママの笑顔が一番!赤ちゃんが元気なら問題なし!【ママは自分を追い込まないで】
今の時代は、ひとり一台スマホを持っている時代。

- 授乳中に子育ての不安なことを検索してる
- 子どもが寝静まってから夜な夜なスマホで検索して悶々としている
そんなことありませんか?
いつでもどこでも検索すればネットに繋がり、不安なことも検索すれば専門家の意見が見られる世の中です。
育児本もたくさん出版されていて、あらゆる情報が手に入ります。
わたしもこうしてネットで情報を発信している張本人なので偉そうなことは言えませんが、そんな世の中なので、情報があふれ過ぎているんだと思います。
育児の情報は、まだまだ都市伝説や伝承レベルのことも溢れていて、医学的に未解明なことが多いこともあり、恐ろしいことに科学的根拠の全くない情報がまことしやかに本に載っていることもあります。
私たちが頼りにしている助産師さん、保健師さん、お医者さんでさえも、こちらがびっくりするほどのエビデンスのない情報を提示してくる方もいらっしゃいます。
素人よりも知識ないとかほんまにプロかいな?って思ってしまいます。
でも、それはこちらにたまたま知識があったから一蹴できますが、もし知識がないままだったら専門家に言われたら信じてしまいますよね。
情報を与える側としては、毎日たくさんの人を相手にする中でルーティーンのように何気なく吐き出している言葉かもしれませんが、赤ちゃんのことを思い悩んでいるママとしては深刻に受け取ってしまうこともありますよね?
たくさんの子どもに触れて、2人目、3人目と育てていくうちに「そんなこと!ww」と笑い飛ばせることがわかってくる子育てでも、誰でも初めての時は特に不安なはずです。
特に、ひとりめの子育ての時は変に力が入って深刻に考えてしまいがちになり、結局は、ママは自分を責めたり追い込んでしてしまう事につながってしまうんですよね。
もちろん、子育てをしていく中で赤ちゃんに異変があったり、ちょっとおかしいなと思うことがあった場合には病院や児童相談所などで相談することも必要になります。
いつも一緒に生活をしていて、観察眼の鋭いママの直感が病気の発見に役立つことは大いにあるからです。
でも、そうでないなら無駄に不安を煽るような発言にはスルーでいいかなと思います。
- ママがまだおっぱいをあげたいと思ったら周りがなんと言おうと続けたらいいんです。(長期授乳はメリットあり)
- 歩くのや言葉を発するのが遅くたって、その子のペースがあるんです。(極度に遅れがない限りは見守ってOK)
- 四六時中だっこしているのだって大変!でも子どもにとってはいつもママとくっつけてなんて幸せなんでしょう。
赤ちゃんが元気ならいろんな細かいことを心配する必要はないです。
それよりも、ママが自分を追い込んでしまい笑顔でいられなくなることの方が心配です。
ママが笑顔で子育てをするのが子どもにとっても一番の安定材料であり、安心して成長することができる環境になるからです。
ママが笑顔で赤ちゃんに関わり、赤ちゃんが元気に健康で成長してくれるためには、外部からの「アドバイス」をスルーする技術も必要なのです。
まとめ
育児中にかけられがちな気になるアドバイスをまとめました。
育児中に必要になる知識は持っておく方が安心です。
ただ、育児本やインターネットには情報が氾濫しており、全ての情報が正しいとは限りません。
膨大な情報の中から本当に必要な情報を精査するのは、育児や家事・仕事に追われるママ・パパにとっては大変なことです。
基本的には、赤ちゃんとよく向き合って、赤ちゃんが元気に成長しているかを観察し、元気だったらそれでOK!
ママが笑顔で赤ちゃんに向き合って、お互いに笑顔で元気に生活できる
これを一番大事にしましょう。
自分に必要ないな、とか向いてないな、と思う情報は華麗にスルーする技術も必要です。
必要以上に情報に振り回されないようにして、楽しい育児ライフを満喫しましょう。




コメント